“伝わる文章”を書くために、意識すべきポイントとは
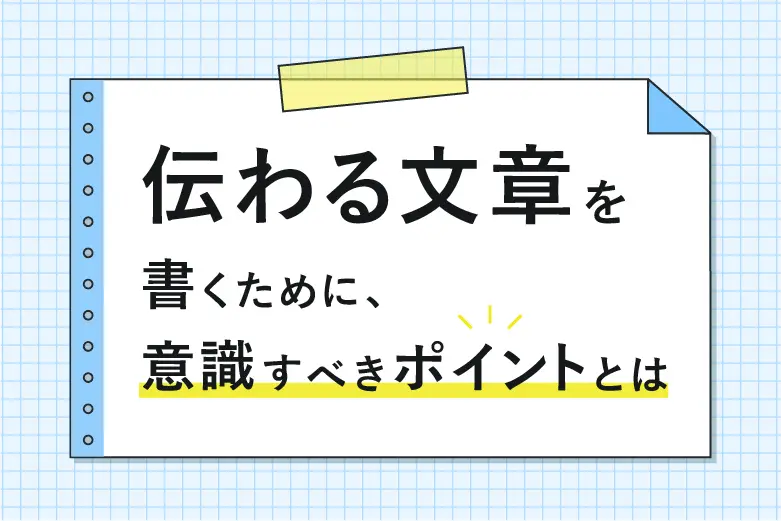
日常生活や仕事に於いて避けては通れないものの、
意外と奥が深くて難しいのが「文章」。
僕は1年前にLYZONへ入社するまで、その文章と多く触れ合う仕事に従事してきました。
今回、社内ブログの担当者から、「『スキル・知識系』というお題でブログを書いてくれ」と依頼をいただいたのですが、人様にお披露目するほどWebディレクターらしいスキルも持ち合わせていないため、“やや人よりも得意”というレベルである「文章」のスキルについて筆を執らせていただこうと思います。
とはいえ、一言に「文章」といっても茫洋としすぎるので、
この記事では文章作成の根幹に関わる「文章を書くための準備と作成の流れ」というテーマで話を進めていきます。
目次
文章作成の工程
文章を書く際の工程を大きく捉えると、だいたい次の流れに集約されます。
- テーマを決める。(決まっている場合もある)
- 大枠の流れ、骨組みを作る。
- 骨組みに対して肉付けを行う。
- 因果関係やつなぎ目に無理はないか、客観的に読み返す。
- 不要な箇所を削ったり、説明不足を補ったりする。
- 再度読み返す、直す、以下完成までエンドレスリピート 。
長い文章も短い文章もこの手順を踏めば、そこそこいい具合に収まってくれるものです。
少々メタではありますが、次の項からはこのブログ記事執筆を例に説明します。
テーマを決める
「スキル・知識」というざっくりとしたお題を与えられたので、まずは冒頭でも述べた理由により、少し範囲を狭めたテーマの方向性として「文章」を設定しました。
方向性が決まったので、続いて具体的な内容を検討します。
Web制作会社のブログに書かれていても違和感がないこと、細かな技法などの好き嫌いに依存しないもの、と消去法で選択肢を潰していき、最終的には「文章作成のおおまかな流れ、押さえるべきポイント」という内容にフォーカスすることにしました。
大枠の流れ、骨組みを作る
テーマが決まったので、今度は文章の中身の検討に移ります。
この記事において読者に伝えるべき内容は、
- なぜWeb制作会社のブログにこんな記事が載っているのか
- 文章を書く工程とは
- 各工程の具体的な内容
であると、まずはざっくりと結論付けました。
しかし、ノウハウ的なものを伝えるには、何かしらの例文や資料引用が必要となります。
それはそれで労力がかかる。
……そうだ、参考資料がないなら今から書こうとしている記事自体を参考資料にしてしまえばいいじゃない。
そんな流れで、本ブログ記事の執筆を通じて文章作成の工程を説明していくという小賢しい手法を選択することになったのでした。
その結果、骨組みを作る作業は極めて簡単になりました。
要は、「文章作成の工程として序盤に記載した箇条書き」の内容そのものが、この文章の骨組みとなったのです。
骨組みに対しての肉付けを行う
あとは骨組みに対してそれぞれ適切な説明を記載し、すべての項目を埋めていくだけの作業となります。
個人的な見解ですが、このとき、肉付けとしての文章は少し多めだと感じるくらいのボリュームで書いてしまうほうが、あとから不足分を補っていくよりも、無理のない自然な仕上がりになると感じています。
木彫りの像を彫る作業をイメージしてください。
木彫りの像の場合、足りなかったものを追加するためにはどうしても無理やり接着剤でくっつけなければいけなくなるけど、削ぎ落とす分には丁寧なヤスリがけさえすれば違和感なく収めることができる。
「文章を書く」として捉えるのではなく、「何かしらの物体を作っている」という意識を持つと少し文章を上手に構成できるようになるのではないでしょうか。
因果関係やつなぎ目に無理はないか、客観的に読み返す
こうして文章を一通り仕上げると、なんとなくそれっぽいものが出来上がってきます。
ただ、これではまだ完璧ではありません。
自分が書いたものであるという事実を頭の中から完全に排除して、知らない人の書いた文章として読み返してください。
書いた人間にしかわからない因果関係的な部分を省略してしまったり、結論ありきで書いた結果無理やりこじつけのような理由と結論が存在していたり、何かしらの破綻が発見できるはずです。
例えば、冒頭の文章はもともと
義務教育や高等教育の課程に於いて、また日常生活や仕事に於いて、避けては通れないものの、意外と奥が深いものが「文章」というやつです。
社内ブログの担当者から、「『スキル・知識系』というお題でブログを書いてくれ」と依頼をいただき、人様にお披露目するほどのWebディレクターらしいスキルも持ち合わせていないため、「文章」にまつわるスキル・知識について筆を執らせていただきます。
という書き出しでした。
しかしこれでは、「なんでこいつが文章についての文章を書いているのか」と、説得力も何もないうえに、
「文章にまつわるスキル・知識が列挙されているかと思って読んだら、文章作成の流れについてしか説明していなかった」という読み手の心構えとのギャップが生じてしまうことになります。
単純な誤字脱字も、客観的に読み進めることで発見できる可能性が上がります。
不要な箇所を削ったり、説明不足を補ったりする
前項で気付いた箇所をひたすら修正します。
話の本筋からは逸脱した余計な文を削り、説明不足の箇所を補っていく。
これもまた肉付けについての項で木彫りの像を例に説明したものと同じようなイメージです。
読み返して、説明不足を補い、本来伝えたかったことが伝わるような内容に修正した結果、現在表示されている冒頭の文章が完成(?)しました。
余談ですが、再三にわたって「文章を書く作業は木彫りの像を彫るようなもの」だと書いてきたものの、
粘土細工的にひたすらパーツごとに文章を書いて整えて、最後にうまい配置で合体させるという手法も選択肢の1つです。
ゴールが見えていない文章を作るときには、粘土細工方式が適している場合もあるので、トライアンドエラーを繰り返して自分に合った進め方を見つけてもらえるとよいかもしれません。
再度読み返し、直す。完成まではその作業をエンドレスリピート
直した箇所を読み返し、さらに直す、という作業を何度も繰り返し続けることで文章は完成に近づいていきます。
時には章の位置をまるごと入れ替えるなど、大胆な修正を行う必要もあります。
最初に作った骨組みは飽くまでも指針。
書いているうちに、直しているうちに収まるべき場所が見えてくるはずです。
まとめ
以上、大まかな流れを説明しましたが、文章を書くうえで特に意識すると、より精度を上げられるポイントとして
- 伝えるべきテーマは何か
- 情報の取捨選択
という2つが挙げられます。
前者は骨組みを作る際、後者は読み返して直す際に念頭に置くべきものです。
意外とこのあたりの作業は弊社のメイン業務でもあるサイト構築、特に設計に於いて意識すべきポイントとして共通する部分があるのかなと、LYZONでの1年間を通じて感じるところがありました。
最後に、今回説明した内容の元となった、僕の原点とも言える教えが網羅された書籍をご紹介します。
「新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング」唐木 元 (著) インプレス、2015年
ライターや編集者という職種以外でも、文章を通じて人に何かを伝える際に役立つ知識がもりだくさんなので、ぜひ興味のある方は手にとってみてください。
編集・ライターを経て、IT分野での経験を積むべく2021年にLYZONへ入社。
2019年以来、日々の生活が筋トレとサウナに支配されている。


